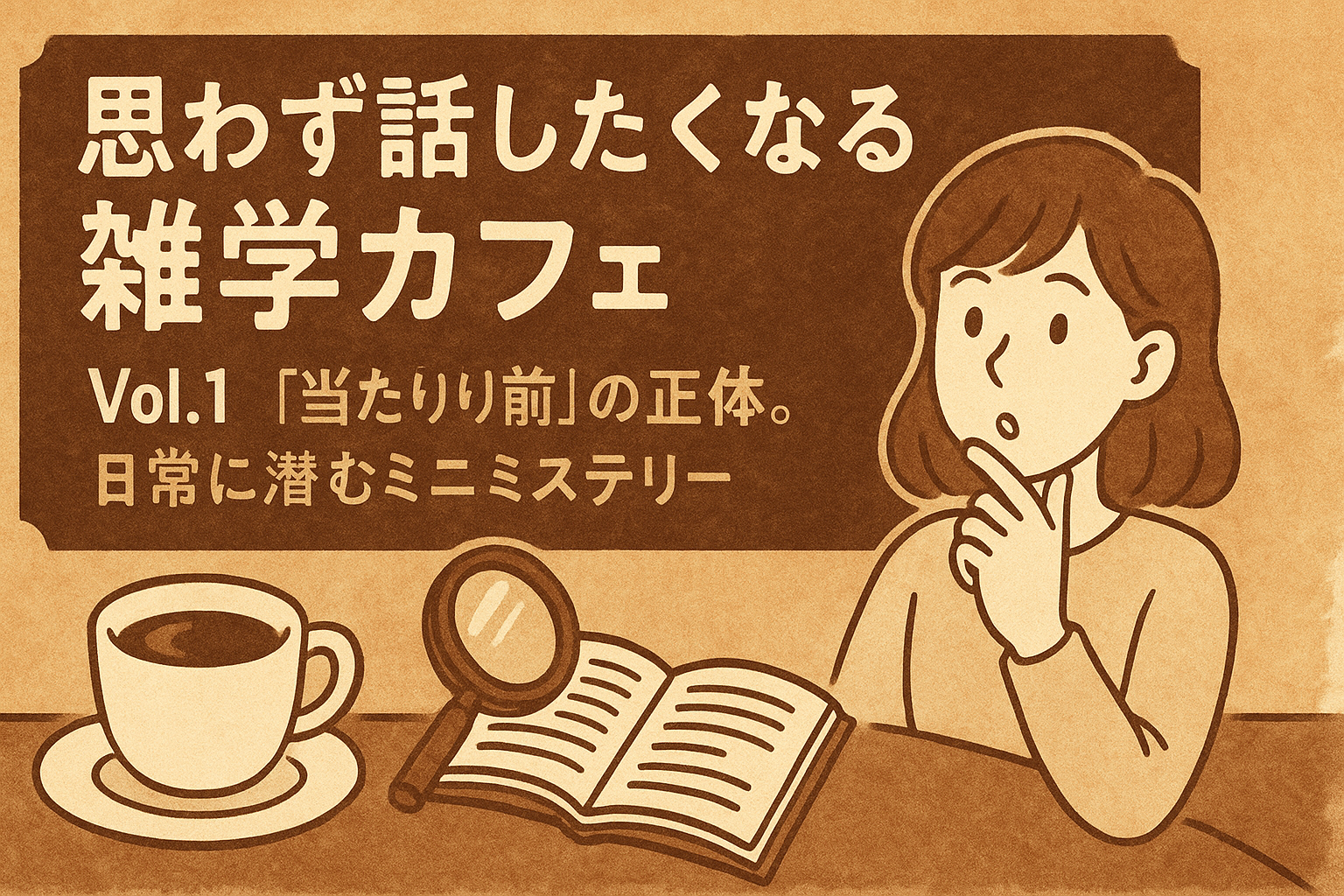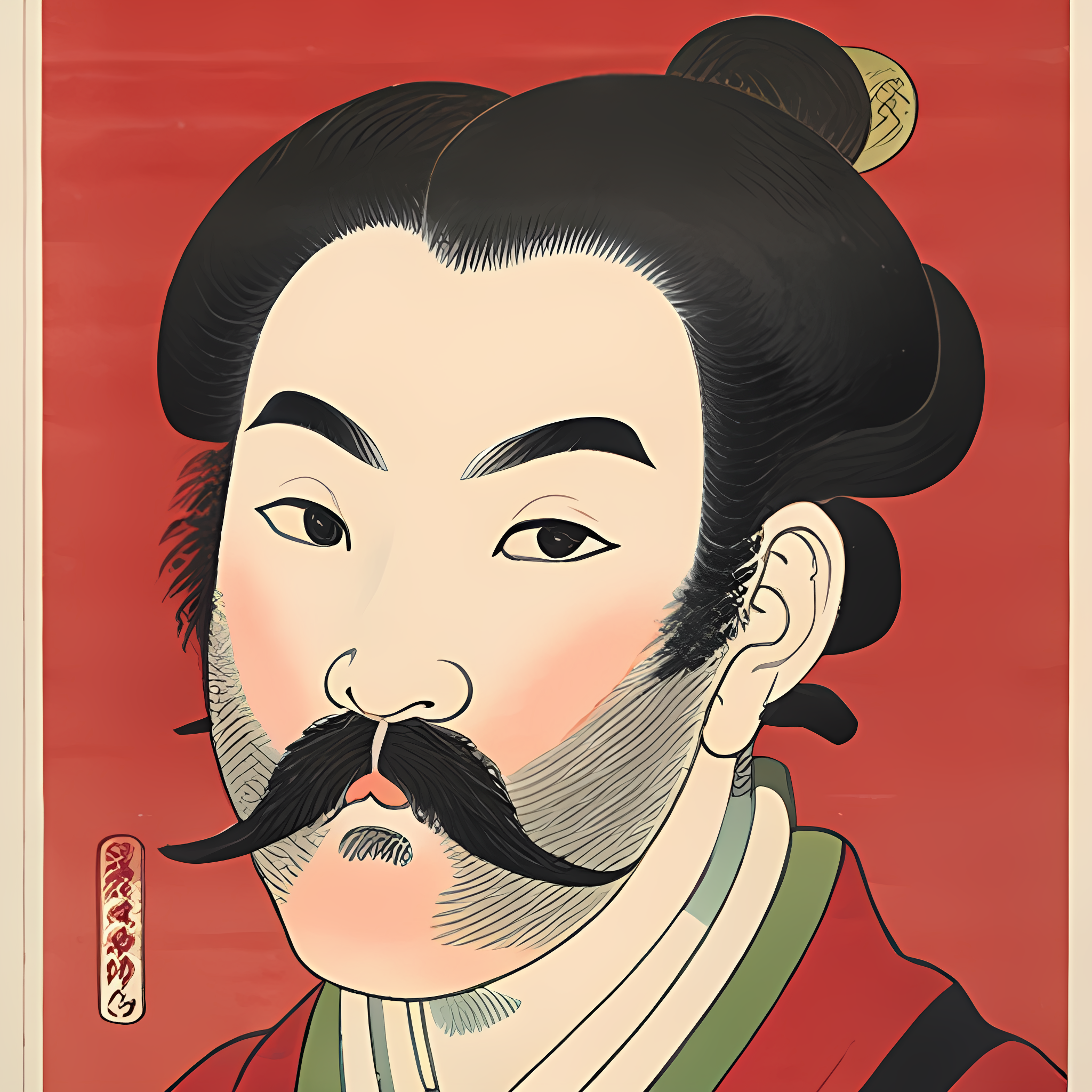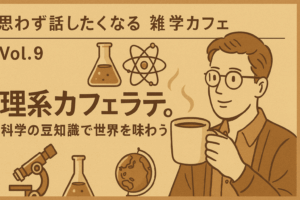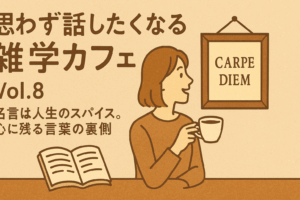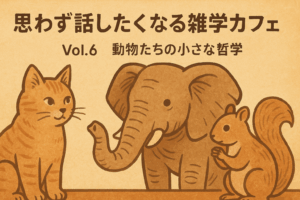☕ 今日のテーマ:
「当たり前」って、誰が決めたんだろう?
■ 「当たり前」は、いつのまにか刷り込まれた“常識”かもしれない
朝、目覚ましのアラームを止めて歯を磨く。信号が青になったら横断歩道を渡る。
コーヒーを飲みながらスマホを眺めて一日が始まる――。
そんな日常の一コマに、私たちはいくつもの「当たり前」を持っています。
でもその一つひとつ、改めて考えてみると少し不思議です。
たとえば、なぜ**信号は「青」で進め」**なのでしょう?
実際の光はどう見ても“緑”に近い色なのに、どうして「青信号」と呼ぶのか。
答えは、日本語の色彩感覚にありました。
昔の日本語には、「青」という言葉が“青・緑・灰色”をすべて含む広い意味を持っていたのです。
「青菜」「青りんご」「青虫」など、緑のものを“青”と呼ぶ名残が今も残っています。
つまり、信号の「青」は言葉の文化が生んだ名残。
誰かが決めたルールではなく、私たちの感覚の歴史が形になった「当たり前」なのです。
■ コーヒーは「黒」じゃない?──色と言葉のすれ違い
コーヒーを「ブラックで」と注文するとき、私たちは当然のように“黒”をイメージします。
けれど、実際のコーヒーは真っ黒ではなく、どちらかといえば深い茶色。
ではなぜ「黒」と呼ばれるようになったのでしょう?
それは、“対比の文化”が関係しています。
日本では、色を「明るい/暗い」で区別する文化がありました。
白(明るい)に対して黒(暗い)という感覚的分類の中で、濃く暗い色=黒と呼ぶ習慣が生まれたのです。
つまり、「ブラックコーヒー」は“砂糖もミルクも入っていない=最も暗い飲み物”という意味。
味覚の世界を、言葉が上手に彩っている例です。
言葉は、物理的な正確さよりも「感じ方」を大切にしてきた――。
その曖昧さこそ、文化の奥行きなのかもしれません。
■ カレンダーの「日曜日が赤い」理由
カレンダーを見れば、日曜日が赤く塗られているのが“当たり前”。
でも、それはいつ、どう決まったのでしょう?
実は日本の暦の「赤と黒」のルールは、明治時代に西洋の暦が導入されたときに生まれました。
当時の印刷技術では、休日を目立たせるために赤インクが使われたのです。
やがてその慣習が定着し、「赤=休み」「黒=平日」という視覚的ルールが社会全体に浸透しました。
面白いのは、海外では必ずしも赤とは限らないこと。
国によっては青や緑で祝日を示すカレンダーもあります。
つまり「赤い日曜日」も、世界共通ではなく**日本独自の“当たり前”**なのです。
私たちは無意識のうちに、文化が塗り分けた「色のルール」の上で生活しているのですね。
■ Wi-Fiマークは“扇形”のままでいいのか?
もう一つ、現代的な“当たり前”を見てみましょう。
街中でよく見かける「Wi-Fiマーク」。
電波の波が扇形に広がるような、あのシンボルです。
でも、あの形――実際の電波の波とは全然違うのをご存じですか?
本当の電波は空間に球状で広がります。
けれど、視覚的に「電波が出ている」ことを伝えるには、扇形が一番わかりやすい。
つまり、科学的な正確さよりも“伝わりやすさ”が優先されたデザインなのです。
日常の中で「見慣れている」ものほど、合理性よりも感覚的な理解で形作られています。
Wi-Fiマークもその一つ。
当たり前のマークの裏に、人間の認知の工夫が潜んでいるんですね。
■ 「当たり前」を疑うと、世界が少し面白くなる
私たちは日々、何千もの“当たり前”に囲まれて生きています。
でも、その一つひとつには、誰かが考え、伝え、受け継いできた物語がある。
「信号の青」も、「コーヒーの黒」も、「日曜日の赤」も。
すべてが、“なんとなく”ではなく、歴史や感覚の積み重ねによって生まれた文化の形です。
当たり前を一枚めくると、そこには人間の創造性が隠れています。
それを少し覗いてみるだけで、毎日がちょっと豊かに見えてくる。
☕ 本日のひとくちメモ
「当たり前」を疑うことは、
世界をもう一度、発見しなおすこと。
次回予告
次回の「雑学カフェ Vol.2」は――
「言葉のエスプレッソ。日本語の深い味わいを少しだけ」。
毎日の会話に潜む“言葉の香り”を、じっくり味わいましょう。